こんにちは。クリリンです。
”大学受験”は人生の中でも最も重要なターニングポイントの一つとされています。
そんな大学受験ですから、まさか「落ちてもいいや」と思いながら勉強している人などいないはず。しかし、大学受験は勝負の世界ですから、受かる人もいれば落ちる人もいます。
もし浪人を前提に考えている方がいれば是非こちらの記事を読んでみてください。

僕は今、京大医学部に在籍していますが、その受験の経験や塾講師バイトの経験などを通して、「その考え方、良くないな。」と感じることが多々あります。
- 自分はこのままで大丈夫なのだろうか。
- 勉強はしているけど、それでも不安になる。
そんな皆さんに向けて、今回は”落ちる受験生の特徴10選”についてお話ししていきます。
もちろん、「ここで話すことが絶対だ」という訳ではありませんが、当てはまるものがある方は是非1度考え方を変えてみてください。
落ちる受験生の特徴ランキングTOP10
”落ちる受験生の特徴10選”をダラダラと書いていっても味気ないので、ここは一つ、ランキング形式にしてみました。
もちろん、
・そもそも勉強量が少ない。
・勉強のやる気がからっきし無い。
といったものは論外ですよ。
大学合格を目指して真剣に取り組んでいるにも関わらず空回りしてしまう要因として、特によくありがちなもの、あるいは致命的なものを上位にしました。
第10位:裏技に頼ろうとしている

特に最近はネット上の情報に多く触れるようになったと思いますが、
「短期間で偏差値10UPする勉強法!」
「◯◯すれば1ヶ月で逆転合格!」
といった謳い文句をよく目にすると思います。こういったものが、れっきとした詐欺まがいのセールストークであることは言うまでもありません。
そんな勉強法があるなら、今頃全員東大に合格してます。
ネット上の情報に限らず、例えば周りの友人が
「この参考書すごく良かった。これやれば絶対数学できるようになる。」
なんていってたら、その参考書のことが気になりますよね。でも違います。それはその人の今まで積み重ねた努力が、その参考書をやることでたまたま開花しただけの話です。あなたと友人とでは、得意分野も違えば、現状の成績も、目指す場所も違うはず。
もちろん、他人の意見を参考にすることで良い結果が導かれることもあるかもしれませんが、何事も鵜呑みにしてはいけません。簡単な話、勉強に裏技は存在せず、努力以上の結果は生まれません。大切なのは、ともかく正攻法を継続すること。その上で他人の意見を参考にしてみるようにしましょう。

第9位:休憩からの再開が遅い
もちろん、勉強の合間に休憩を取ることは勉強効率を高める上で大切なことであるのは言うまでもありません。しかし、皆さんは本当に勉強効率を上げるための休憩の取り方をしていますでしょうか。
「ちょっと休憩〜」と思ってスマホを触ってしまったが最後に、気付けば30分、1時間と時間を浪費してしまい、ひどい時には「今日はもういいや」とそのまま勉強を再開することなく終えてしまうこともあるかもしれませんね。
大学受験合格に向け勢いで勉強を始めることの出来る人は多いですが、1度休憩に入ってしまえばすぐに勉強を再開できる人は意外にも少なく感じます。極端な話、東大・京大といった超難関大学に合格するような人たちは、”勉強”の合間には科目を変えた”勉強”で気分転換しながら平気で5時間くらい連続で勉強しますし、休憩するにしてもトイレに行ったり、ちょっと立ち上がってみたりするだけで、5分で勉強を再開します。
確かに、集中の仕方は人それぞれですし、最近では「人間の集中力は◯◯時間が限界」といった研究もなされているようですが、事実として超難関大学に合格するような人たちはそのくらい勉強している人が多いというお話です。
しかし、誰もがそのような勉強量を真似しろと言うのはあまりに酷かもしれません。そこで、勉強と休憩のサイクルで1番意識すべき重要な点は「勉強の再開」です。ポイントは、勉強に疲れて休憩に入るとき、「◯時◯◯分に再開する!」といった形で、あらかじめ再開する時間を決めておくこと。
絶対に後ろ倒しにしないこと!
特に受験生の方々は、”休憩の取り方”については少し敏感になるように心掛けてみて下さい。
第8位:スキマ時間を活用していない
「スキマ時間を上手く活用することは、大学受験を勝ち抜くための第1歩」だということはネット上でもあちらこちらで言われていることです。
皆さんも親であれ学校の先生であれ、スキマ時間の重要性について1度は言われたことがあるのではないでしょうか。その謂れの通り、スキマ時間はまさに偉大。
はっきり言って、スキマ時間を活用せずして受験に成功した人など見たことがありません。
5分あれば、英単語30個に目を通せます。
15分あれば、スタディサプリの動画1本流せます。これが積み重なれば、大きな差が生まれてしまうことは想像に難くないでしょう。
スキマ時間は日常のあちこちに潜んでいます。受験に成功したければ、むしろスキマ時間を絞り出すくらいの気持ちで積極的に活用していきましょう。

第7位:受験に「運」が必要だと思っている

「受験に運は関係しないか?」と聞かれれば、関係はします。
例えば、
・得意分野が出題された。
・直前に勉強したことが出題された。
・勘で書いたことが合っていた。
など、細かなことを言ってしまえばキリがないほど受験に運要素は絡んでくることは事実です。
しかし、それはあくまでも試験が開始されてからのお話。試験が開始されるまでの間はいくらでも努力することができ、運に依らない”実力”を身につけることができますし、実力を身につけた人にこそ”運”の幅も広がります。
すなわち、ある程度実力が身についている人は、
・得意分野が広がる。
・直前に詰め込める知識量が増える。
・勘の精度も上がる。(3択が2択になる など)
というように、運と実力は密接に関係していることがお分かりいただけると思います。
人事を尽くして天命を待つ。天命を待つのは、”人事”を尽くしてからです。
受験の世界では、努力した人にこそ”運”が宿ります。
試験開始前に神頼みするのはあまりにも早すぎるのです。
第6位:学校の先生・定期試験をバカにしている
「学校の先生は自分の目指す大学より低いレベルの大学出身だから参考にならない。」
「塾や模試の勉強に追われて学校の定期試験の勉強が出来なかったから、学校の成績が悪いのはしょうがない。」
このように思ったことがある方は案外多いのではないでしょうか。
確かに(特に公立高校でありがちなことですが)、学校の先生があまりにも未熟で説明が分かりづらかったり、定期試験でとんでもなく的外れな出題をしてくる先生方もいらっしゃるのかもしれません。しかし、大抵の場合は生徒自身の傲慢さ・計画性のなさ・努力不足の表れだと僕は思うのです。
”学校”は基本的には皆さんが毎日のように通う場所であり、1番学習ペースを作りやすい環境です。にも関わらず、「学校の先生よりも塾の先生の方が頼りになる。」という先入観のもと、学校の先生を見下し、塾での勉強を優先して学校での勉強は疎かにする。
こういった生徒が、最近少なくないように感じます。
その結果、学習ペースを乱し、「学校の授業が邪魔」と言いつつさらに成績を落とし、最終的には落第します。
綺麗事抜きに、大学受験に合格する人の多くは、学校の授業をものすごく大切にしていますし、学校の先生も最大限に利用しています。皆さんの周りでも、基本的に”成績の良い人”というのは、学校の定期試験でもしっかりと得点をとっているのではないでしょうか。
もちろん(先述の通り)、大切にすべき授業とそうでない授業もあるかもしれませんので、結局は皆さん次第ですが、案外学校の授業からでも学べることは多いはず。
今1度、謙虚になって、学校での勉強について見直してみてはいかがでしょう。
第5位:他人・環境のせいにしている
勉強に限らず、何事も人のせいにしていては成長できません。
もちろん自責思考が強すぎるのは問題ですが、
・自分で解決できることはないか?
・自分に原因があるのではないか?
と自問・詮索してみることで成長の鍵となるヒントを見つけられることが多々あります。
成績があがらないのは、
・塾に行かせてくれない親のせい。
・学校の先生の教え方が悪いせい。
・地方で教育サポートが整っていないせい。
と、他人や環境のせいにするのは受験業界ではご法度。
確かに、他人や環境によって受験の有利不利が関わってくるのも事実ですが、それを嘆いていても仕方がありません。
環境は受験生一人ひとりで違い、それぞれが与えられた条件のもとで努力しています。
特に、最近では優良な参考書もたくさん出版されていますし、インターネット上でも有益な受験に関する情報が溢れており、教育格差を理由に諦めてしまうにはもったいなすぎる世の中です。受験に成功する人は、「他人や環境が自分に何をしてくれるか」ではなく「与えられた他人や環境をどう利用するか」という思考をベースに物事を考えられる人なのです。
第4位:インプットよがりの勉強をしている

「勉強で大切なのはインプットよりもアウトプット」という話を聞いたことがある人は多いはず。情報が脳に定着するのはインプットの時よりもアウトプットの時だと言われています。
具体的に、コロンビア大学の研究により、最も勉強効率が高まるインプットとアウトプットの黄金比が導かれており、その比率は「インプット:アウトプット=3:7」。
つまり、アウトプットのほうが多くなければならないということです。
中でも、特に大切にしていただきたいのは「問題を解く」ということ。
大学入試の問題というのは、その”問題の解き方”におおよそ共通する特徴があります。
例えば、皆さんが4択の問題を出題するとしたら、その選択肢はどのように決めるでしょうか。
きっと、似たような選択肢や間違えやすい選択肢を出題して、受験生を騙しにかかろうとしますよね。このように、問題を解くためには”問題を解くための知識”が必要であり、それを身につけるためには「問題を解く」ことが最も手っ取り早いのです。
これが、アウトプット重視の勉強で得点効率が上がるカラクリであり、ただ漫然とインプットよがりの勉強をしていてもせっかくの努力が水の泡となりやすい。
心当たりのある方は、是非インプットとアウトプットの勉強比について見直してみて下さい。
第3位:模試・試験の結果と向き合っていない
「学校の試験は質が悪いから復習してもしょうがない。」
「いつの模試結果が返ってきたんだよ。E判定だけどこの頃は出来なかっただけ。」
こうして、試験の結果と向き合うことが重要であることは分かってるけど、心のどこかでその現実から逃げてしまっている人は多いのではないでしょうか。
結果の悪い試験と向き合うことは決して気持ちの良いものではありませんので、逃げてしまう気持ちも大いに分かります。
しかし、着実に成績を伸ばしていく人というのは、「これでもか!」というほど試験結果を自己分析しています。
・問題との相性が悪かっただけ。
・ケアレスミスが多かっただけ。
・時間配分を間違えただけ。
・たまたま解けなかっただけ。
そういった中身のない振り返りで終わらせるのではなく、
・どういった点で相性が悪いのか。
・何故ケアレスミスが多かったのか。
・どうしたら時間配分を間違えずに済むのか。
・「たまたま」を「確実」にするためにはどうするか。
など、ともかく徹底的な対策を講じていかなければ成績は上がっていきません。「第4位」でもお話した通り、問題には”問題を解くための知識”が必ず存在し、それを習得するためにも模試・試験を復習することはやはり非常に大切なのです。
その重要性を再認識し、特に結果の悪い模試・試験こそ綿密に向き合って、徹底的に自己分析を行うようにしていきましょう。

第2位:過去問の重要性を理解していない
皆さんも大学受験合格に向け、様々な参考書やテキストに取り組んでいくであろうと思われますが、その中でも最も大切な資料は「過去問」であることは絶対に忘れてはいけません。
受験勉強は長期的な視点で戦略を練る必要があるので、その長い過程の間に「本番で出題される問題を解く」という最大の目標を見失い、参考書の問題に固執してしまっている人は案外多いのではないでしょうか。
確かに、
「参考書の問題が解けなければ、過去問も解けるようにならない。」
という意見もあるかもしれませんが、参考書を解くのはあくまでも「本番で出題される問題を解く」ための手段であることを忘れてはならないというお話です。
どんなに勉強ができる人でも、大学入試本番までの時間で参考書の全ての問題を完璧にこなせる人などいません。
もちろん、全てを完璧にするくらいの勢いで取り組むことは大切ですけどね。(苦笑)
大学入試の問題には必ず大学ごとに出題傾向があります。大切なのは、「出題傾向を把握し、それに沿った勉強をする」という視点で普段の勉強に取り組むことです。
これこそが究極的な勉強効率を産む勉強法であり、限られた時間でも合格を勝ち取る人の思考なのです。
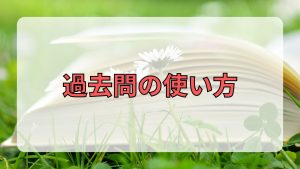
第1位:”才能”の壁から逃げている

落ちる受験生の特徴ランキングTOP10堂々の第1位は「”才能”の壁から逃げている」こと。
皆さんも、例えば学校や塾に
「あの人は頭の作りが違うから…。」
と感じてしまうような人はいませんでしょうか。
もちろん、受験に才能が関係ないかと言われれば、関係が無いわけではありません。しかし、それよりも大切なことは、
「あの人は何故あんなにも勉強ができるのだろう。」
と、”why?”を問い続けること。
大抵の場合、その人が勉強できる所以は、幼い頃からの積み重ねを含めた”勉強量”という圧倒的な努力であることに気付くはず。だとすれば、「あの人に追いつくためには、自分はあの人の2倍努力しなきゃ!」となるのが合格する人の発想です。
多くの人は、大きな実力差を目の前にしたら諦めてしまいますが、出来る人は”why?”を考える。
この”why?”を考える習慣こそが、勉強のみならず、生き方そのものにおいても非常に重要な思考習慣であり、”地頭の良さ”にも直結してきます。
”才能”の壁から逃げるのではなく、”才能を磨く”という視点のもと、自分にできることを考えることの出来る人が、大学合格のみならず、社会にも貢献できる人材へと躍進していくのではないでしょうか。

最後に
以上、落ちる受験生の特徴ランキングTOP10でした。
この記事で言いたかったことをまとめると、
- 他人や環境のせいにせず、自分に出来ることを考える。
- 結局は正攻法で積んだ”勉強量”がモノを言う。
- 過去問を解くための勉強をしよう。
これだけは頭の隅にでも置いておきましょう。
また、この記事では受験において非常に大切なことがたくさん詰まった記事になっていますので、定期的に確認しにくるのも良いかもしれません。
この記事に訪れた全ての人の健闘を祈っております。



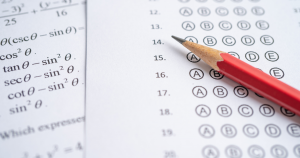



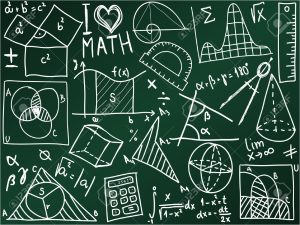



コメント