みなさんこんにちは、MORIです。
今回の記事は、塾や予備校に通わずに、参考書だけで京大英語7割を獲得した僕が、どのように英語を勉強したのか、ありのままに語っていきたいと思います。
帰国子女でもなければ、英語が得意だったわけでもない、凡人の僕がどのように勉強していたのか紹介していきます。
僕の勉強法が正しいなんて思ってないし、もっと良い勉強法はあると思います。
しかし、塾や予備校に通わずに、英語の受験勉強を進めていきたいと思っている人の参考になればと思って書いています。
どの勉強の仕方が身になったのか、どの勉強の仕方があまり効果がなかったのかすべて話していきたいと思っています。
京大に限らず、旧帝大などの難関国立大を目指す人は参考になる部分があると思うので、京大志望者以外にも、独学で英語を勉強したいと思っている人にはぜひ読んでいただきたいと思います。
独学で勉強し、現役で京大英語7割をとった勉強法をありのままに話します。
良かったこと、悪かったことをすべて話すので、勉強の参考になればと思います。
大前提ー大学受験の英語の勉強法

まず最初に述べておきたいのですが、受験英語を勉強する際に、○○大学を目指すから△△という勉強をする、というのは少々浅はかかと思います。
というのも、どこの大学を受けようが、大きく分けると受験英語で求められる能力は、(リスニングを除く)
①単語
②文法
③英文解釈
④英作文
の4つで構成されています。
記述がない私立大学などは④の英作文がいらないことも少なくないのですが、出題形式の差こそあれ、①~④がどの大学の入試でも求められているのです。
そのため、どの大学を志望するにしても、基本的な力の4つを身に付けるために勉強は欠かせないのです。
基礎固めの段階(過去問演習に入るまで)では、どの受験生も①~④すべての力を付けていく必要があります。
①~④がどのような力なのか、そしてどのような勉強法で身に付けることができるのかについては、京大医学部のクリリンさんやLeeくんがとても分かりやすくまとめてくれているので、下に紹介する二つに記事を見ていただけたらと思います。
こちらの記事は、公立高校から京大医学部に現役合格したクリリンさんが、英語の勉強法とおすすめの参考書を紹介してくれている記事です。受験英語の勉強法をステップ立てて解説してくれているので、英語の勉強の仕方やどの参考書を使って勉強したらいいのかわからない人にはぜひ読んでほしいと思います。
>>関連記事:【京大医学部】英語の勉強法&オススメ参考書
こちらの記事は、圧倒的な東大合格率の高さを有している、大学受験界における最強の塾、鉄緑会に通い京大医学部に現役合格したLeeくんが、受験英語のすべてを解説してくれています。受験英語の全体像がつかめていない人には絶対に読んでほしい記事になっています。
>>関連記事:【京大医学部】受験英語のすべて-塾、参考書、何から勉強したらいいのかについて
それでは①~④の力を僕がどのように勉強したのか、どのように勉強するとうまくいかなかったのか説明していきたいと思います。
①単語力をつけるための参考書と勉強法
使っていた単語帳と気を付けるべきこと
僕が使っていた単語帳は「システム英単語」と「鉄壁」の二冊です。
シス単は学校で配られたもので、鉄壁は自分で買ったものです。
シス単はフレーズで覚えることで英作文でも生かせたし、鉄壁は派生語が多く乗っていたりイラストや語源が乗っていたりしてとても覚えやすかったです。
どちらもおすすめの単語帳です。
大学受験に関する記事や、大学受験に関するYouTuberなど、いろんな人が言っていますが、
単語帳は何でもいいから一冊を仕上げる
ことが大切です。
僕は実際に2冊つかったのでわかることですが、2冊使って勉強すると、どっちかの単語帳、または、両方が中途半端になってしまうことが起こってしまいやすいです。
自分は、1年生の時までシス単を使っていて、2年生になるタイミングで、鉄壁をメイン単語帳として使い始めました。
1年生までは良かったのですが、2年生になってからは、学校の単語テストはシス単で作られているのに自分が勉強しているのは鉄壁、というねじれた関係になってしまいました。
その結果、単語テストの前だけシス単、普段は鉄壁、という風になってしまい、結果的に1冊に使う時間が減りどちらも中途半端でした。
今考えれば、鉄壁を買わずにシス単でずっと勉強するか、シス単の単語テストを捨ててでも鉄壁だけでで勉強するか、のどちらかにしぼっておいた方が、単語帳を効率よく仕上げられたのではないかと思います。
そのため、二回目ですが、
単語帳は何でもいいから一冊を仕上げる
ことを徹底してほしいと思います。
具体的な勉強法
英単語はどの時期でも勉強しましたが、特に力を入れて勉強していたのは1年生の時です。
単語は知っていれば知っているほどいいので、できれば1年生か2年生の時点で完成されることが望ましです。
単語を覚える具体的な勉強法ですが、原則通り、赤シートで隠したり、音読したりして、回数を繰り返すことを重視していました。
オーソドックスな勉強法なので、書いて覚えることはやめる、ということ以外には特に注意すべきことはありません。
※どの単語帳を使うか
先ほど単語帳は何でもいい、と言いましたが、基本的には学校で配られたものを使うのがおすすめです。
それは学校での勉強の時間を少しでも無駄にしないためです。
正直に言って僕は学校のシス単のテストの時間を無駄にしていたので、時間がもったいなかったなと感じています。
また、ぼくは鉄壁を使いましたが、ボリュームがすごいので、回数を繰り返すのが結構しんどかったです。
そのため、鉄壁はよくできた単語帳で、いいところもたくさん知っていますが、ボリュームに圧倒され、回数を重ねることができないということを懸念して、僕は鉄壁をあまりお勧めはしません。
②文法力をつけるための参考書と勉強法

使っていた参考書
僕は、「アルティメット」という文法がかなり詳しく解説された参考書と、「ヴィンテージ」、「スクランブル」という文法の問題集を使って勉強しました。
アルティメットとスクランブルは学校で配られたもので、ヴィンテージは自分で買ったものです。
文法の問題集は、おそらく学校で1冊買うことになるので、自分で買う必要はないかと思います。
また、どの参考書も大差がないように感じるので、何を使っても、1冊を仕上げることができればよいと思います。
具体的な勉強法
文法を重点的に勉強したのは、1年生から2年生の前半です。
単語同様に、文法は英語の勉強の基礎になるので、早い段階での完成が求められます。
僕の勉強の進め方としては、アルティメットで書いてあることを読んで文法事項をインプットして、ヴィンテージで実際に問題を解いてアウトプットする、という勉強を繰り返していました。
ヴィンテージは1つの問題につき3回正解するまで回数を重ねます。
一般的に言われている使い方で勉強したので、特に注意すべきことはありません。
ただここでも1つだけ問題がありました。
ヴィンテージを自分で買った、というところで気づく人もいるかもしれませんが、ヴィンテージとスクランブルは同じ役割の問題集なので、単語帳と同じように学校の授業と自分の勉強とのねじれが生まれてしまいました。
そのため、今考えればですが、学校の勉強を無駄にしないために、学校で配られたスクランブルを使って勉強すればよかったと感じています。

③英文解釈力をつけるための参考書と勉強法
使っていた参考書
僕が英文解釈の勉強で使った参考書は「ポレポレ」と「英文読解の透視図」です。
どちらも自分で買った参考書です。
両方とも、昔から使われている参考書で、難関大受験生からの支持はすごいものになっています。
基本的には1冊やれば十分だと思いますが、知識や経験を増やすことや、練習を積むことができるので、2冊やるのも悪くないと思います。
僕の印象では、ポレポレよりも透視図の方が、いろいろなテーマを扱っていて好みでした。
学校では英文解釈の授業はなかなかないと思うので、独学で勉強する人は、1冊は英文解釈の参考書が必要です。
僕があげた二つでもいいですし、ほかのものでも何でもいいので、なにか1冊、早めに買うことをお勧めします。
1冊なにか買うとすれば、僕のおすすめはポレポレです。
薄くて、取り組みやすいというのが1番の理由です。
ポレポレのついて徹底的に解説した記事があるので、ぜひ読んでいただければと思います。
英文解釈の参考書を持っていないという方は、下のリンクからポレポレか透視図を購入してみてください。
一冊終わった後に英文の読み方が変わったことを実感できるはずです。
こちらの記事は、ポレポレについて、徹底的に解説しています。
英文解釈の参考書選びに迷っている人には、ぜひ読んでほしいと思います!!!
>>関連記事:【徹底解説】ポレポレ英文読解プロセス50の評判・レベル・使い方まとめ
実際の勉強法
僕が英文解釈の参考書に取り組んだ時期は、2年生と3年生の時です。
単語と文法がある程度完成してからの勉強をお勧めします。
僕はまず初めにポレポレをやって透視図をやりました。
僕は例題のたびに和訳を紙に書いていましたが、今思えば、
英文解釈の勉強の時は紙に和訳を書くのは効率が悪い
です。
なぜなら、英文解釈の勉強が進んでいないときに、英文解釈の参考書に書いてある例題の英文の構造を初見で見抜くのはかなり無理があるからです。
実際に僕は、紙に和訳を書いてしまって英文解釈の勉強がなかなか進まず、時間を使いすぎたという経験があります。
また、構文を間違ってとらえてしまう状態で和訳をしてもいい和訳の練習にはなりません。
和訳は英文解釈の勉強が一通り終わってから取り組むべきです。
以上のことから、英文解釈の参考書をやる時は、頭の中で構文がどうなっているか5分くらい考えてみて、わからなかったら解説をすぐ見る、というやり方を僕はお勧めします。
④英作文力をつけるための参考書と勉強法
使っていた参考書
僕が英作文の勉強のために使っていたのは、「ドラゴンイングリッシュ」と「英作文が面白いほどかける本」です。
どちらも英語受験界の大御所、竹岡広信先生の著書です。
どちらも受験英語界では高い評価を受けている参考書で、困ったらこれらを使ったらいいと思います。
ドラゴンイングリッシュは、例文が100個ついていて、それを覚えることで英作文の構文の骨格として使おうとする目的で使う人が多い参考書です。
薄めの参考書なので、英作文の応急処置をしたい人にお勧めです。
英作文が面白いほどかける本(おも英と略すことにします)は、英作文で頻出の言い回しや表現などに対応する例題と練習問題がついていて、1冊でインプットもアウトプットもこなせるよくできたおすすめの参考書です。
おも英はボリュームがある参考書で、ドラゴンイングリッシュに書かれていることはおも英にもほとんど書かれているので、おも英やるならドラゴンイングリッシュはいらないかなと思います。
実際の勉強法
英作文の勉強は2年生の最初に学校の授業で始まったのですが、自分で参考書を使って勉強し始めたのは2年生の後半からです。
英作文も英文解釈と同様に単語と文法が完成してからの勉強をお勧めします。
僕の勉強方法としては、ドラゴンイングリッシュの例文を音読などして覚えるところから始めました。
しかし、きちんと覚えることなくおも英の勉強を始めてしまったため、正直無駄になっていしまったかなと思います。
おも英の勉強法は、まず頻出の構文や言い回し、例題の英訳を覚えることをスタートにしました。
大体覚えたなと思ったら練習問題を解いてみて解説と照らし合わせて、良かったところと悪かったところを洗いだす、ということをやっていきました。
英作文は記述が求められるので、例題の日本語を紙に書いて英訳するなど、アウトプットの比重は重めにすることを心がけていました。
過去問について

過去問の重要性
①~④の勉強が進んだら、次に進めるべきことは過去問を解き進めることです。
入試での得点を大幅に上げるために過去問演習は欠かせません。
どんなに実力のある人でも、問題の形式や傾向がわからない試験で高得点を取るのは難しい、ということは簡単にわかると思います。
そのため、過去問や模試の過去問を使って、京大英語の形式、内容に近い問題を解きなれておくというのはとても重要です。
また、以前出題されたものに似た問題が出ることもありますし、得点アップには欠かせません。
特に京大の場合は、ほかの大学と比べてとても問題の癖が強いので、対策なしでは高得点は難しいものの、対策がしやすいとも言えます。
そのため、僕は正直言えば英語がめっちゃできる、というわけではありませんでしたが、京大英語の対策の効果もあってか、本番は7割取ることができました。
実際の進め方
過去問の重要性はこの辺にして、実際に過去問をどう進めていったか解説したいと思います。
僕が過去問を解き始めたのは高3の夏休みでした。
ゴールデンウィークにちらっと問題の形式を見てみたことはありましたが、本格的に始めたのは高3の夏休みです。
過去問を解くときに一番大切にしていたのは、大問ごとに解くのではなく、時間を測って1年分を1セットで絶対に解いていたことです。
その理由は、本番の試験では、時間配分、問題の難易度の見極め、どこで点を取り、どこを捨てるのか、という勝負になるからです。
その力は実際にセットで通しで解くことによってしか身に付きません。
よってセットで過去問を解くのはとても重要なのです。
どの年度から説いたかといえば、始めは2010年あたりの問題を解いて、そこから進んだり戻ったりを繰り返して、大体15年分くらいの過去問を解きました。
普通の受験生は、過去問は10~15年分と夏秋に受けるオープンと実戦、そして駿台と河合から出ている模試の過去問を何年分か解ければ十分だと思います。
僕がやっていた復習法
ぼくは問題を解くのもそうですが、復習を最も大事にしていました。
分からない単語は全部調べて、復習しやすいように単語帳に書き加えました。
英作文は解答解説とにらめっこして、時間をかけて自分になかった知識をいれれるだけいれていきます。
そして解いた過去問は、1週間ごとに定期的に復習をして忘れることがないようにしていました。
解きなおしができればベストなのですが、なかなか時間が厳しかったので、長文も英作文も音読メインでたまに解きなおす、という感じで復習していました。
復習してもどうしても抜け落ちはありますが、その抜け落ちは回数を重ねれば重ねるほど少なくなるため、回数を重ねることを意識していました。
復習に使っていたのは、復習ノートと駿台から出ている、京大入試詳解25年です。
京大入試詳解は、いわゆる京大の青本の英語で、25年分の問題、解答解説がのっています。
京大の青本は質が高いことで評判で、特に英語の解説には過去問の解説を見るたびに感動していました。
問題の解答だけでなく、なぜその解答になるのか、なぜこの場所が答えの根拠になるのか、問題を解くための背景知識は何なのか、など、詳しすぎると言ってもいいくらいの解説がなされています。
解答解説の質からして、赤本ではなく絶対に青本を使うことをお勧めします。(ちなみに赤本も青本も同じくらいの値段です。)
大きな書店でないと、この青本は売っていないことが多いので、ぜひ下のリンクから買ってみてください。
この記事のまとめ
この記事では、僕が京大英語で7割取った勉強の中で、失敗したことやどのように勉強することがおすすめなのかすべて説明してきました。
人それぞれ勉強法があって、合う合わないがあるとは思いますが、この記事を読んだみなさんは、僕と同じ失敗はしないようにして、少しでも勉強の効率を上げていただければと思います。
京大英語は対策をしたらしただけ、言い換えれば、勉強をしただけ伸びる科目なので、僕の勉強法を参考に勉強してもらえたら幸いです。
二回目になってしまいますが、過去問をするときには絶対に青本を使ってほしいと思います。
絶対に勉強の質が上がること間違いなしです。



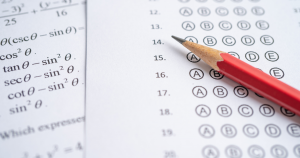
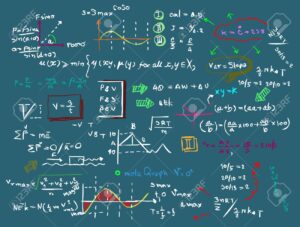



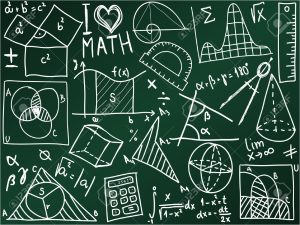


コメント