こんにちは。クリリンです。
難関大学を受験する多くの高校生にとって、これまでの合格者がどれほど勉強しているのか、あるいは周りのライバル受験生がどれほど勉強しているのか、気になるところですよね。
もちろん、ただ長時間勉強していれば合格することができるのかと言われれば決してそう言うわけではありませんが、やはり大学受験結果と勉強時間については大きな相関関係があることも事実です。
高校生活の過ごし方を考える一つの基準としても、目安となる勉強時間は欲しいところですよね。
この記事では、難関大学合格者がおおよそどのくらいの勉強時間を確保してきたのかを高1〜3の時期別にそれぞれまとめていこうと思います。
難関大学合格者の勉強時間
一般に、「難関大学」といえば
- 旧帝大、医学部
- 東工大、一橋
- 早稲田、慶應
は誰もが認める難関大学であり、その下に
- 東京外大
- 上智、東京理科大
- GMARCH、関関同立
あたりが続いてくるでしょうか。
まぁ、人によって基準は違ってくると思いますが、「自分が難関大学だと思っている」ならばそれは立派な難関大学です。
以上のような大学を受験する人たちが、高校時代どれほど勉強してきたかについて、東進ハイスクールが公表しているちょっぴり有名なデータ(2017年)があります。
その調査結果は以下の通り。ただし、学校の授業時間は勉強時間に含みません。

難関大学
①国立大学:東京大学、北海道大学、東北大学、名古屋大学、大阪大学、九州大学、東京工業大学、一橋大学、東京外国語大学
②私立大学:早稲田大学、慶應義塾大学
難関大学現役合格者の高校3年間のおおよその平均勉強時間は、ズバリ
4093時間
という結果になりました。
逆に不合格者の平均勉強時間は、3759時間。
すなわち、高校3年間トータルで334時間の開きがあるわけです。
これはどれほどの数字なのか、パッと見ではよく分からないかもしれませんね。
「4000時間」という規模の中の「334時間」というのは相対的に小さく感じるかもしれません。
でも実は、これはかなり大きな違い。
334時間あったら、どれだけ勉強ができるでしょうか。
例えば、1日10時間の猛勉強をするとしても1ヶ月以上の月日を要する量であり、これは夏休みが丸々1個分余分に与えられていることに相当します。
こう見ると、「334時間」は確かに合否に関わってきそうな数字だと感じますよね。
もう少し詳しく見るために、学年別の勉強時間を見ていきましょう。
難関大学合格者の高1の勉強時間

東進ハイスクールのデータによれば、
難関大学に現役合格する生徒の高1の平均勉強時間は757時間。
一方、現役不合格者の高1の平均勉強時間は637時間。
1年間で単純計算すれば、高1の勉強時間は「1日あたり2時間」が基準になってくるでしょう。
皆さんはどうでしょうか。高1のテスト週間でもない「何でもない休日」に、少しでも勉強に取り組めているでしょうか。
合格者と不合格者の間には高1で既に120時間の差がついているわけです。
確かに、「120時間」は1日あたりに換算してしまえば約20分です。しかし、それだけに「もう少しだけやっておこう」という”1日のちょっとした積み重ね”が将来的に大きな差を生むということは是非とも弁えておくべき事実なのです。
難関大学合格者の高2の勉強時間

東進ハイスクールのデータによれば、
難関大学に現役合格する生徒の高2の平均勉強時間は1132時間。
一方、現役不合格者の高2の平均勉強時間は954時間。
1年間で単純計算すれば、高2の勉強時間は「1日あたり3時間」が基準になってくるでしょう。
特に高2の夏休みあたりからは本格的に受験勉強を始めるという生徒も増えてくるため、「高2の夏休みからスタートに踏み切れるか」というのは受験結果を左右する1つの大きなラインになってくるのかもしれませんね。
合格者と不合格者の間には高2では178時間の差がついています。
これは高1〜3の中で最も大きく差の開いている数字であり、「高2でいかに多くの勉強時間を確保できるか」というのがライバル受験生と差をつける最も簡単な方法であるとも言えるでしょう。
難関大学合格者の高3の勉強時間

高3は受験生にとって一番大切な時期というのは言うまでもありません。
東進ハイスクールのデータによれば、
難関大学に現役合格する生徒の高3の平均勉強時間は2204時間。
一方、現役不合格者の高3の平均勉強時間は2168時間。
1年間で単純計算すれば、高3の勉強時間は「1日あたり6時間」が基準になってくるでしょう。
勘違いされてしまってはいけないので言っておきますが、「難関大学」と言えどもその中身はピンキリ。はっきり言って、東大受験生は1日6時間では間に合いません。
ここで、もう一つベネッセが公表しているデータを貼っておきます。

2014年とちょっと古めのデータですが、ベネッセ独自の調査によれば、
東大・京大受験生の高3の勉強時間は当然のように10時間を越してきます。
色々なデータが出てきて「結局どれくらい勉強すればいいの?」と混乱してしまうかもしれませんが、ひとまずは「データは参考程度に。」と思っておきましょう。
また東進ハイスクールのデータによれば、合格者と不合格者の間には高3では36時間しか差がついていません。
これは高1〜3の中で最も差の開いていない数字であり、「難関大学受験生は高3で勉強するのは”当然”であるため、受験生になってからの勉強時間ではあまり差がつかない」と言えます。
逆に言えば、難関大学受験において大切なのは、「受験生時代の過ごし方」というよりも「高1、2年でいかに早くから受験を意識した勉強に取り組めるか」であるということが言えそうです。
勉強時間のデータを鵜呑みにしてはいけない理由
さて、ここまで難関大学合格者の具体的な勉強時間についてのデータをまとめてきましたが、やはりこれらのデータは鵜呑みにしてはいけません。
理由の一つに、これらのデータは高校入学以降のデータであるから。
特に難関大学受験者の場合、中学受験をしていて既に中学生の頃から大学受験に向けた勉強を開始していたり、幼い頃からしっかりとした幼児教育を受けているなど、データには表されていない”これまでの人生の積み重ね”に違いがあるのです。
恐らく合格者の勉強時間は少なめに見積もられています。場合によっては、5000時間以上必要なことだってあるでしょう。
そして理由のもう一つに、勉強時間は正確に計れるものではないから。
最近では勉強時間を記録するアプリなども開発されているので、「高校生時代の正確な勉強時間が分かる」という方もいらっしゃるかもしれませんが、それでも大半の受験生らは正確な勉強時間など記憶しておらず、「大体これくらいかな〜」という感覚で調査に回答しているはず。
さらに言えば、これらの”勉強時間”というのは「机に向かった時間」を指す場合がほとんどであり、ちょっとボーッとしてしまった時間や、勉強に直結しない作業をしている時間なども含まれている可能性があります。
今受験生として勉強している皆さんにもそういった時間は少なからず出てきてしまいますよね。
簡単な話、勉強時間の調査には限界がある。
これは当然のお話かもしれませんが、難関大学合格に必要な勉強時間は人それぞれです。
もちろん、上記のデータをある程度参考にするのは良いかもしれませんが、
結局のところ大切なのは「今の自分と志望校との距離を客観的に把握し、それに基づいて必要な勉強時間を確保すること」としか言いようがないのです。
勉強時間は多いに越したことはない
「難関大学合格に必要な勉強時間は人それぞれ」とはいえ、
”今の自分と志望校との距離”がいまいちピンとこないから困ってるんだよ!
と思われた方が多いかもしれません。
そこで皆さんに今一度思い出していただきたいのは、「勉強時間は多いに越したことはない」ということ。
そもそも、大学受験の合否は”試験本番の得点”で全てが決まる訳であり、なにも「短時間の勉強で成果を出せ。」と言われてる訳ではありませんし、「勉強時間が長いのだから出来て当たり前だ。」と傾斜をかけられる訳でもありません。
つまり、勉強時間は長く確保したほうが有利。
この事実だけは拭えません。
特に難関大学を受験するともなれば、中高一貫校などで中学時代から既に大学受験レベルの勉強を始めている人や、浪人してより多く勉強時間を確保している人たちがライバルとなる訳です。
そんなライバルを目の前にして「必要最低限の勉強時間で合格したい。」という考えがある時点で敗北は確定です。
ともかく貪欲に、がむしゃらに、勉強時間を確保することが合格への1番の近道なのです。

僕自身も公立中高から京大医学部に現役合格していますが、高校入学時点から既に中高一貫校の生徒に差をつけられているという事実があったため、狂ったように勉強していましたね。高校3年間で8000時間以上は勉強していました。
”勉強時間”と同じくらい”質”も大切
ここまで勉強時間を多く確保する重要性についてお話ししてきましたが、ただ漫然と長時間取り組むだけでは事足りず、当然”質”も意識した勉強をする必要があります。
ただし、ここで気をつけていただきたいのは”勉強時間”と”質”は「同じくらい」大切だということ。
質を担保すれば勉強時間を妥協していいというものでもありません。
そもそも、ある程度勉強時間を確保しなければ勉強の質など上がっていくはずがありません。
最初、右も左も分からない状態では、とりあえず行き当たりばったりで勉強を始めるしかないため、すぐに成績は上がりません。しかし、諦めずに勉強を積み重ねていくと、自分のすべきこと(=質)がだんだんと分かってきて、徐々に成績が上がりはじめる。その後、またしばらくは成績が停滞したりしますが、少しレベルを下げてみたり、手をつけやすい教科や分野からはじめてみる等、再び勉強の質の上げ方が分かってきて、また成績が上がりはじめます。
これは”質量転化の法則”と言われており、「量の積み重ねが質の向上につながる」「量を積み重ねる事で自然と質も高まる」という考え方です。
>>関連記事:質量転化の法則のカラクリ-脳死での積み上げはNGです【改善のコツを解説】
一見遠回りしているかのように見えるかもしれませんが、これは誰しもが避けられないルートであり、だからこそ難関大学受験においては勉強の”量”と”質”はどちらもが大切な要素なのです。
>>関連記事:勉強は質と量どっちが大事か【凡人に大切なのは『質より量』の心構えです】
まとめ
難関大学に合格するためには、高校3年間だけでも4000時間を超える勉強時間が必要であるとされています。
ただし、この「4000時間」という数字に過度な信頼をおいてしまうのは禁物。
もちろん、この数字を一つの基準として勉強に取り組むことは悪いことではありませんが、決して「4000時間勉強すれば受かる」という訳ではありません。
特に、東大・京大を目指すのであれば4000時間では足りないと思います。
大切なのは「今の自分と志望校との距離を客観的に把握し、それに基づいて必要な勉強時間を確保すること」。
そして、”今の自分と志望校との距離”を測るためには、他でもなく”勉強”してみないことには何も始らない訳であり、ある程度”勉強”をすることで初めて中身のある質の良い勉強ができるようになるのです。
ほとんどの人は、”勉強”し始めてみてようやく「間に合わない」ことに気付く。
現役で合格する生徒は驚異的な勉強時間を確保している人がほとんどであり、「必要最低限の努力で合格したい」と思った時点で負けは必至なのです。
難関大学を本気で目指すのであれば、「少しでも早く始めて、最大限の勉強時間を確保すること」に尽力していきましょう。



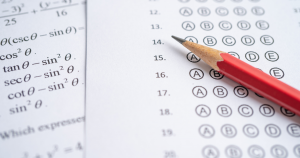



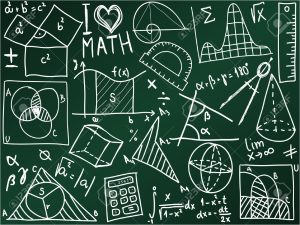



コメント