こんにちは。クリリンです。
“4当5落”
これは日本で昔から言い伝えられている言葉で、
「睡眠時間は1日4時間まで削って勉強すれば合格し、5時間眠ってしまえば落第する。」
と言う意味です。
もちろん、これはあくまでも非科学的な根性論に過ぎないわけですが、実際のところ睡眠時間を削ってまでして勉強することは本当に有益なのか。
そして、勉強にベストな睡眠時間は何時間なのか。
今回はそんなお話をしていきます。
勉強にベストな睡眠時間は人によって違う

睡眠時間は生活様式によって影響を受ける。睡眠不足が続くと、より長い睡眠が必要になることが示されている。また、いくつかの研究では、日中活発に過ごした場合、より長い睡眠が必要になることが示されている。季節によっても睡眠時間は変化する。睡眠が不足すれば、日中の眠気が強くなり、種々の心身の問題が生じる。一方で、長く眠ることを意識しすぎると睡眠が浅くなり中途覚醒が増加する。〜(中略)〜健康保持の観点からは、日中しっかり覚醒して過ごせるかどうかを睡眠充足の目安として、心身の不調や問題 があるときには睡眠習慣について振り返ることが重要である 。
厚生労働省『健康づくりのための睡眠指針2014』
要するに、人間の最適な睡眠時間について、絶対的な基準は無いということです。
いわゆる、
“ショートスリーパー”
“ロングスリーパー”
と呼ばれる人がいるように、睡眠は体質や性、年齢など個人的な要因に影響されており、5時間未満の短時間の睡眠で大丈夫な人から、成人でも10時間以上の睡眠を必要とする人までさまざまです。
また、睡眠は身体が必要としている時間以上の睡眠をとることは不可能と言われており、睡眠時間にこだわり過ぎるとかえって睡眠が浅くなったり、不眠に陥ることが多くなります。
「睡眠時間は人それぞれ、日中の眠気で困らなければ十分」と、睡眠時間にはこだわらなくて良いというのが専門家の見解なのです。
朝型VS夜型-勉強に効率的なのはどっちか【むやみな早起きは逆効果】
記憶を効果的に定着させる睡眠時間とは

睡眠と記憶の定着には密接な関係があることは皆さんもご存知の方が多いと思います。
では、記憶を効果的に定着させるためには、何時間の睡眠が必要なのか。
甲南大学知能情報学部の前田多章准教授は、理想の睡眠時間は7時間30分であると提唱しています。
予備校比較ガイド『「4当5落」は危険!受験生は7時間30分の睡眠がオススメ』
人間の睡眠には「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」の2つが存在し、この2つの睡眠が1セットになって、大体90分ごとに繰り返し行われています。
このサイクルを繰り返して記憶が定着することがわかっており、このセット数が多いほど、記憶の定着も進むということになります。
つまり、7時間30分の睡眠を取れば「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」のサイクルを5セット繰り返すことができ、これが理想の睡眠時間は7時間30分であるとされる所以です。
ところが、
東大が行った調査によると、東大生の睡眠時間は、平均6時間35分です。
記憶の学校『「記憶力の高さ」と「睡眠」の関係性。寝ないことのデメリットも紹介』
もちろん、「東大生のやり方が正しい」と断言するわけではありませんが、先ほども申し上げました通り、勉強をする上で最適な睡眠の取り方もやはり個々人で変わってくるものです。
規範的な枠に捕われることなく、あくまでも「日中の眠気で困らなければ十分」という視点を大事にしてみてください。
逆に、日中の眠気に困らされているようであれば、それは要改善です。
睡眠時間を削ることによる悪影響
さて、ここまで「睡眠時間は自分自身と相談して決めるべきだ」という旨で書いてきましたが、なお無理してまで睡眠時間を削って勉強するのは脳や心身に悪影響を及ぼします。
ここでは睡眠不足によって引き起こされる懸念事項をお話しします。
逆に言えば、ここでお話しする症状が出るようであれば、睡眠は足りていないということになります。
記憶力の著明な低下
先ほども申し上げた通り、睡眠と記憶の定着には密接な関係があります。
無理までして睡眠を削れば、当然記憶が定着する効率は悪くなります。
意思決定や問題解決力で極めて重要とされている前頭葉と頭頂葉の活動が減ってしまう。また脳のシナプスを再形成(記憶の定着)する働きを阻害する活動が活性化する。
BBCニュース『睡眠不足は脳にどう影響する』
これが現代脳科学の結論です。
集中力の欠如
睡眠不足が続くと集中力が欠如していきます。
皆さんも、勉強の最中に眠気に襲われれば、「行動パフォーマンスが低下している」とを感じたことがあると思います。
せっかく勉強時間を増やすにしても、集中できていないのであれば元も子もありません。
眠気で勉強に集中できないのであれば、「大人しく寝る」が吉です。
自律神経失調症
自律神経失調症は自律神経のバランスが乱れることで発生します。
睡眠不足によって交感神経が優位になり十分な休息が取れなくなることで、心身に以下のような悪影響が及びます。
- 血圧の上昇
- イライラ、怒りっぽくなる
- 頭痛
勉強とは直接的には関係ないことかもしれませんが、やはり体調はしっかり整えて、勉強する態勢をつくっておくのは大切なことですね。
そもそも「睡眠時間を削らなければならない状況」が間違い
そもそも論になってしまいますが。
睡眠時間を削ろうとする元々の理由というのは、
「勉強時間が足りないから」
というのが大きいでしょう。
そしてその原因は、
「勉強を始めるのが遅かった。」
ほとんどはコレに尽きると思います。
少し厳しい言い方になりますが、「睡眠時間を削らなければならない状況」は、過去のあなたが勉強をサボったことが原因であり、早くから勉強を始めていれば無理して睡眠時間を削ろうとしないはずです。
睡眠時間を確保するための最善の策は、
「勉強を早めに始めて余裕を持つこと」
であることはくれぐれも忘れないようにしてください。
最後に:それでも勉強時間が足りない場合
ここまで書いてきた通り、勉強にベストな睡眠時間は個々人で違ってくるわけですが、
「自分は睡眠時間を多く取らないと身体が持たない・・」
「たくさん寝ていてはどうしても勉強時間が足りない・・」
正直なところ、こう言った人たちに対して
「心ゆくまで寝てください!」
とアドバイス出来るほど受験の世界は甘くありません。
そこで、睡眠時間を削らずとも、勉強時間をより多く確保する方法をお話ししておきます。
変えるべきは「睡眠時間」ではなく、「スキマ時間」
個々人で必要な睡眠時間が決まっている以上、睡眠時間を大きく削っての生活サイクルは合理的ではありません。
そこで大切な視点は、
「睡眠時間を削る」
ではなく、
「スキマ時間をより有効に活用する」
ということです。
スキマ時間の代表的な例は、「電車に乗っている時間」などの移動時間だと思います。
しかし、それ以外にも
- 授業中、すでに理解出来ていることを解説されている時間
- 何の勉強をするか迷っている時間
- 何も考えずボーッとしてる時間
など、日常の中にはより有効に活用できるスキマ時間が散りばめられています。
以下の記事でスキマ時間の具体的な使い方について解説していますので、参考にしてみてください。
>>関連記事:スキマ時間の最大限活用勉強法-スキマ時間の使い方で合否が決まる
仮眠の効果が絶大です
勉強時間が足りず、睡眠時間すらも惜しい。
そういった人たちに是非ともオススメしたいのが「仮眠」です。
結論から言うと、「昼の睡眠は夜の睡眠の3倍の効果がある」というのが、今の医学的見地です。
すなわち、30分の昼寝を2回すれば、単純計算で夜の睡眠の3時間に相当する効果が得られるのです。
もちろん、だからと言って夜の睡眠を疎かにして良いわけではありませんが、「仮眠」には
- 認知能力上昇
- 注意力上昇
- 記憶力上昇
と、勉強に嬉しい様々な効果があることが立証されています。
ただし、仮眠には注意しなければならないポイントもありますので、以下の記事を参考に、自分の生活サイクルに取り入れてみてください。
>>関連記事:勉強効率を上げる「仮眠」のポイント-仮眠の効果が絶大です



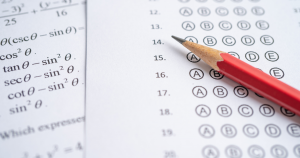



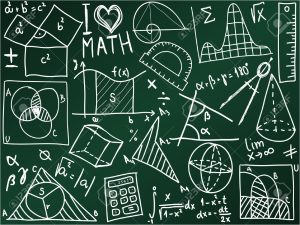



コメント