みなさんこんにちは、MORIです。
高校の数学の授業や、課題、もしくは自習で数研出版の「4STEP」を使ってる人、多いのではないでしょうか?
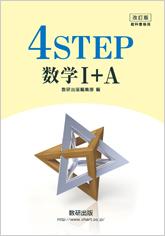
学校ではじめて習った範囲の練習問題から、その範囲の応用問題まで載っていて、使いやすいと思っている人も多いのではないかと思います。
しかし、いま4STEPで勉強している人からすればあまり聞きたくないことかもしれませんが、京大に現役合格した僕は、
「4STEPは数学の自習にはおすすめしません」

多くの人が学校で買って、実際に多くの人に使われている問題集なのに、なぜ僕が4STEPを数学の自習におすすめしない理由を、4STEPの特徴をしたうえで、説明していきます。
そして、4STEPの代わりに、何を使って勉強するのが良いのかも説明していきます。
4STEPの特徴
1.掲載されている問題
4STEPには、教科書レベルの問題、定期テストレベルの問題、そして易しめの入試問題まで、幅広くの問題が掲載されています。
また、教科書レベル~定期テストレベルの問題がとても多く掲載されていることも特徴的です。
2.構成
以下は、数研出版の4STEP数学Ⅰ+Aの説明からの引用ですが、数学Ⅱ+B、数学Ⅲでも、同様です。
基本から発展まで幅広く豊富に問題を収録。着実に力が身につきます。
STEP A … 基礎力の養成。教科書の例・例題・問レベル。
改訂版 教科書傍用 4STEP 数学I+A
STEP B … 応用力の養成。教科書の応用例題・節末・章末レベル。
発展問題 … 発展学習。教科書では取り扱われなかったが重要な問題。
演習問題 … 入試対策。AとBの2段階に分け,章末に収録。
A問題は教科書の基礎、B問題は教科書の難しい問題、発展問題と演習問題は易しめの入試問題、といった感じです。
有名大や難関大を目指す受験生からすれば、最終的に発展問題と演習問題が解けるレベルには到達したいところです。
4STEPを自習におすすめしない理由
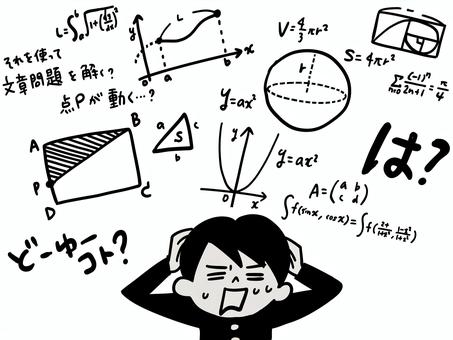
なぜ僕が4STEPを数学の自習におすすめしないのか、理由を完結に述べると、
4STEPは自習にむいた教材ではない
からです。
なぜ4STEPが数学の自習に向いていないと言えるのか、4つのポイントを解説していきます。
1.4STEPの問題集としての立ち位置(一番重要なポイント)
4STEPがどのような目的で作られた問題集か皆さん知っているでしょうか?
答えから先に言うと、
「学校の先生が授業や課題で使うため」
です。

授業と併用するためなんてよく言われますが、僕の出身高校では4STEPの問題が乗った課題のプリントが出されていました。
4STEPの解答解説が配布されないのは、授業や配布プリントなどで、学校の先生が問題を解説することが前提になっているからです。
そう考えると、生徒が解答解説を持っていたら、授業や課題で都合が悪いですよね。
そのため、解答解説が配られない、なんてことが起こるんです。
学校で使いやすいように作られているため、自習用ではないのです。
2.解答解説がないため、復習ができない
1で解説したことと重なる内容なのですが、4STEPの解答解説が配られない、という学校がとても多いです。
配られたとしても、学年末とか、1冊の範囲が全部終わったときとかで、使いたいときに使うことができない状態だと思います。(実際に僕が通うっていた高校もそうでした。)
成績が伸びるタイミングは、問題を解いた後に復習した時のみです。
そのため、解いた問題は、解き終わってすぐに復習するのが理想的です。
しかし、解答解説がない4STEPは、問題を解いても、冊子の後ろについている略解しか見ることができません。
略解だけでは、自分の解き方や答案が正しいかなんてわからないし、もし間違っていた場合は、何が間違っているのかすらわかりません。
以上を踏まえれば、略解しかない4STEPが自習に向いていないことは言うまでもないと思います。
3.解答解説があっても、簡素すぎてわかりにくい

4STEPの別冊の解答解説は、問題番号とその解答しかついていません。
解答だけだと、なぜその考え方になるのか、なぜその解き方にするのか、まるでわかりません。
数学が得意な人は大丈夫かもしれませんが、苦手な人は、解答が何を言っていいるかわからない、なんてこともあると思います。
基本的に解説は詳しい方が勉強しやすいため、解説が簡素で不親切な4STEPは自習には向いていないと言えます。
4.一冊で勉強が完結しない
志望する大学にもよりますが、4STEPだけの勉強で到達できるレベルはあまり高くなく、十分ではないと言えます。
扱われている問題のレベルとしては、ほかの問題集や参考書に引けを取らないかもしれませんが、方針があまり書かれていないことや、解説解説の簡素さからして、数学の実力を効率よく伸ばすのが難しいです。
また、青チャートや基礎問題精選のように、例題が詳しく解説されていれば一冊で自習もしやすいですが、4STEPはそれが難しく、一冊で数学の勉強が進めるのが難しいです。
4STEPではなくて、何を使って勉強すればいいのか

僕が4STEPをお勧めしない理由は、上で説明した通りですが、それでは実際に何を使って数学の勉強をすればいいのか、解説していきます。
ずばり、僕がおすすめするのは青チャート、フォーカスゴールド、レジェンド、といった網羅系参考書です。
網羅系参考書は、4STEPに載っているレベルの問題に加えて、それより高いレベルの旧帝大レベルの問題まで掲載されています。
それに解答解説も充実しており、4STEPにはない、なぜその考え方になるのか、なぜその解き方にするのか、が網羅系参考書にはしっかりかかれています。
網羅系参考書は分厚く、量が多いのがネックですが、重要な部分だけを正しいやり方で進めることができれば、消化できない量ではありません。
そして、間違いなく4STEPよりも自習がしやすく成績を伸ばしやすい教材です。
詳しい網羅系参考書の使い方は、以下の記事にまとめているのでぜひ読んでほしいと思います。
網羅系参考書の特徴、構成、使い方を全部解説した記事です。
数学の実力を効率よく伸ばしたい人には絶対に見てほしい内容です!!!!
>>関連記事:《難関大受験》数学の網羅系参考書の使い方ー青チャート・フォーカスゴールド・レジェンドの使い方
4STEPの使い方
この記事では、4STEPを数学の自習に使うことをおすすめしませんが、もし使うとすれば、どのように使うと効果的か解説していきます。
基本的には、次の2つの使い方がおすすめです。
逆に言えば、以下の2つ以外の使い方はあまりお勧めできません。
1.定期テスト対策

学校の定期テストの対策に4STEPの問題に取り組むのはとても有効です。
というのも、4STEPは教科書傍用問題集という名前からわかるように、教科書との相性が最もいいからです。
定期テストが教科書の練習問題や章末問題ぐらいのレベルで作られるという学校がほとんどだと思います。
また、4STEPについている類題から定期テストの問題が出題されるという学校も多いと思います。
そのため、定期テスト対策のために、4STEPに問題を解いて、その範囲を固めるというのは良い勉強法だと思います。
2.分野別に演習を積みたいとき
自分、図形と方程式の問題もっと解いて練習したいな、
みたいに、特定の分野の問題演習をしたいって思うことって少なくないですよね。
でも、使ってる他の参考書の問題は解ききってしまって新しい問題がない、なんてこともあると思います。
その時に使えるのが、4STEPの問題です。
4STEPのレベルが高めの問題は定期テストの対策や学校の授業で扱ってない部分も多いと思うので、初見の問題演習にうまく使えるのではないかと思います。
ほかの参考書の問題がある程度解けるのであれば、解説も簡素なもので問題ないですし、新しい問題が解けるので、4STEPの問題を使うのがおすすめです。
この記事のまとめ
この記事では、現役京大生の僕が、4STEPを使って勉強することをお勧めしない理由を解説してきました。
4STEPの難点は、なんといっても解答解説が雑で不親切だし、復習がしにくい、という点にあります。
そのため、4STEPではなくて、青チャートなどの網羅系参考書を使って勉強をするのがおすすめです。
学校で配られたからそのまま使う、のではなくて、自分の成績を伸ばすために、効率よく勉強することが大切です。
4STEPではなく、復習がしやすい教材を使ってほしいと思います!!


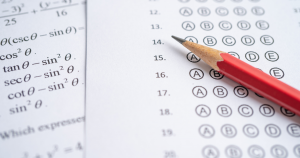
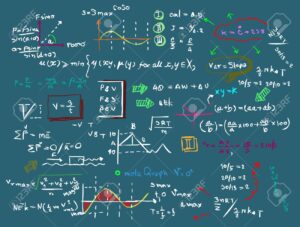



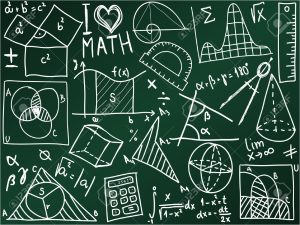


コメント
コメント一覧 (2件)
親戚の子どもや従業員の子どもの数学の勉強方法について、アドバイスを求められたことがあります。
今だと武田塾で略解しかない4ステップをこき下ろすこともあっってか、瀬戸内の自称進学校でも解答が配られるようになりました。
私たちの時代は解答は配られず数学嫌いの生徒を増産していました。
高校3年になってから解けなければ答えを見る、そして覚えるという勉強方法が正しいと初めて知りました。
高一の数学の先生は略解しかないからいいんだ、何時間でも考え抜けと言ってました。
今から思うと、あの先生の一言はとても罪作りに思えます。
でも福岡のトップ高校でも解答は配らなかったんですね、驚きました。
うちの高校だと東大京大医学部だと別格、誰も数学は解法を覚えるなどとは言わず、神様扱いされるのを楽しんでいたようにも思えます。
私は現役時には成績はイマイチでしたが、浪人して京大理学部に行くと担任の先生に言ったら、せせら笑われました。何浪しても無理だと。
この一言は自分の人生を左右までさせられました。
現役時は京大理学部を来年のため記念受験。
一浪時にはそれほどは伸びず、二浪突入。
二浪時はなんとかなるのではまで行きましたが不合格。
滑り止めの早大理工に進学。
野球の早慶戦を見れば京大への未練は断ち切れると思い神宮に行きましたが、諦めがつかなかったというよりは、私を小馬鹿にした担任を見返してやりたいの気持ちから仮面浪人。
親にもバレてしまい家庭の中は嵐の状態に。
こんなときに開業歯科医をしていて子どものいない叔父から「歯学部に行くなら学費も払ってやるし、今の車もやる」と言われたのと、また京大落ちたらどうしようという恐怖から地元の歯学部に行きました。
大学3年までは生理学生化学の勉強もあり、歯学部も悪くないと感じていました。
ところが大学4年になると職人まがいの実習、ここで医学部落ちの学生さんたちは歯学部に来て後悔するのがでてきます。私はもともと図画工作が好きだったので、これでいいかで学生生活を終えて現在は叔父の後継として、瀬戸内でしがない町歯医者を続けています。
最後に、地方の高校生たちは学校が絶対に正しい、先生は間違ったことを言わないと信じているのが大半です。
そんな中で学校の副教材の取り扱いが間違っていると京大生から貴重な発信をされているのはとても有意義に感じています。
ありがたいお言葉ありがとうこざいます。
インターネットやSNSも普及して、受験を取り巻く環境もどんどん変わっているかと思いますが、それでもやはり受験勉強における教育格差の問題は改善されていないように思います。
4ステップの解答に関してですが、略解しか載っていないからこそ思考力が高められるという考えも分からないわけではありません。本来の数学というものは覚えるのではなく、考えに考え抜くのが重要なのでしょう。ただ、限られた時間しかない高校生、浪人生か受験勉強を効率的に進め、ライバルとの競走に勝ち抜くことを目標とするなら、そういったやり方は遠回りになってしまいますよね。
そういった事情も理由の1つで私、は4ステップはおすすめしないですね。
東大や京大に合格する層が以前どのような勉強をしていたのか、私には想像もつきませんが、最近の層はやはり解法暗記から勉強を始めていると感じますね。そういった理由からも私は解法暗記から入るとこを勧めています。
拙い記事に、貴重なコメントを寄せて頂きありがとうございました。